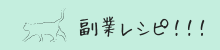◆プロローグ:「アイデアは若者の特権」だと思っていませんか?
ビジネス関連の雑誌・記事においては、イノベーションやクリエイティビティが毎日のように話題になります。新しい事業アイデアをどう出すか? 次のプロダクトの種をどう見つけるか? そのたびに、多くの人がこう思っているはずです。
「創造性は若さのうちにしか発揮できないのでは?」
実際、テック業界やスタートアップの世界では、20代や30代で世界を変えるような事業を立ち上げる人が目立ちます。だからこそ、「自分も早く成果を出さなければ」と焦ってしまう人も多いのではないでしょうか。
しかし、茂木健一郎さんが語るように、脳の仕組みから見ると「創造性は年齢とともにむしろ高まる」ことがあるのです。本稿ではその背景にある脳科学的な知見と、ビジネススクールで学ぶ私たちがキャリアや経営にどう活かせるかを、じっくり紐解いていきます。
◆第1章:「ぼーっとする力」が創造のカギ──脳科学が明かすひらめきの正体
● デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)って何?
私たちが仕事に集中しているとき、脳の「実行系ネットワーク」が活性化しています。計算、分析、計画などをする場面ですね。
一方で、ぼーっとしていたり、散歩中にふと思いついたりする時に働くのが「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」です。このDMNが創造性と深く関係していることが、神経科学の研究でわかってきました。
実は、アイデアの“タネ”は、DMNが働いているときに生まれているのです。
● 年齢を重ねると、DMNが強くなる?
茂木さんの記事では、「年齢を重ねた人の方がひらめきが多い」とされていますが、その理由の一つがこのDMNの活性化です。
年齢を重ねると、脳の「自動化能力」や「連想力」が強くなります。過去の経験や知識を大量に持っているからこそ、DMNがそれらを再構成しやすくなるのです。
これは、単なる記憶力や情報処理速度とは違う、「熟成された知的活動」だと言えるでしょう。
◆第2章:創造性には“型”がある──年齢と得意なタイプの関係
● 創造性は3つのタイプに分けられる
| タイプ | 特徴 | 得意な年齢層 |
|---|---|---|
| 発想型 | 多様な視点から自由なアイデアを出す | 若年層 |
| 統合型 | 情報を組み合わせて全体を構造化する | 中年層 |
| 洞察型 | 突然のひらめきで本質に気づく | シニア層 |
この分類で重要なのは、それぞれの創造性が「年齢によって失われる」ものではなく、「役割や形が変わっていく」ものであるということ。
● ビジネス的視点で考えると…
ビジネスにおける戦略立案、組織開発、イノベーションなどの領域では、3つの創造性がすべて必要です。
-
若手の「発想型」は、新規事業のアイデア出しに有効
-
中堅の「統合型」は、組織再編や戦略構築に強み
-
シニアの「洞察型」は、企業文化や意思決定に深みを与える
つまり、「創造性のタイプの違い=組織内での役割の違い」として見ると、より納得感があります。
◆第3章:「年齢による硬直化」は神話だった?
● 加齢は本当に“保守的”を生むのか?
多くの人は、「年を取ると保守的になって新しいことを嫌う」と思い込んでいます。しかし、実際には“過去に縛られている人”と“過去を活かせる人”の違いなのです。
実際、行動経済学や心理学でも、「経験を意味づける力」は年齢とともに高まると言われています。
-
若いころ:知識が点で存在している状態
-
中年以降:知識が線や面としてつながり、概念化されている状態
だからこそ、ひとつの経験から“本質”を抽出する力、つまり「洞察力」が育つわけです。
● 「アンラーニング」との関係
「アンラーニング(学習の手放し)」は、年齢にかかわらず必要な概念です。
アンラーニング(Unlearning)とは、これまでの経験や知識、価値観を一度手放し、新たな考え方や行動様式を受け入れるためのプロセスを指します。単に「忘れる」ことではなく、「古い枠組みにとらわれず柔軟に再構築する」ことが本質です。特にビジネス環境が急速に変化する現代においては、過去の成功体験がむしろ足かせになることもあります。アンラーニングは、自分の思考の癖や固定観念に気づき、それを見直す力であり、新しい知見や視点を取り入れるための重要なスキルといえます。
実は、年齢を重ねた人の方が、自分の過去としっかり向き合えるぶん、意外とアンラーニングに成功しやすいのです。
◆第4章:「組織内ひらめき力」の設計図──世代を超えたチームの作り方
● 多様な世代が共に働く組織のメリット
「多様性(Diversity)」という言葉はよく聞きますが、「年齢の多様性」について語られることは意外と少ないものです。
「年齢の多様性」とは、組織やチーム内に若年層からシニア層まで、幅広い年齢層のメンバーが共に働く状態を指します。年齢が異なれば、経験値や価値観、考え方、得意な仕事のスタイルも異なります。例えば、若手は新しい技術やトレンドへの感度が高く、柔軟な発想力に優れます。一方、中高年は経験に基づく判断力や人間関係の構築力に強みがあります。こうした世代間の違いを組み合わせることで、多角的な視点や発想が生まれ、より豊かなアイデアや意思決定が可能になるのです。
創造性という観点では、年齢の違いは極めて有益な「思考スタイルの違い」を生むのです。
➤ 例:イノベーション・ラボの設計
-
20代:市場トレンドや若年層の感性
-
30-40代:事業モデルや実行性の担保
-
50-60代:戦略的意義や文化的インパクトの視点
このように「思考のタイムスパン」や「価値判断軸」が異なる人々がチームになることで、より立体的で多面的な議論が可能になります。
◆第5章:創造性は鍛えられる!──“ひらめく人”の習慣5選
年齢に関係なく、ひらめき力を高めることはできます。以下は脳科学的にも効果があるとされている習慣です。
● ① 散歩や自然との接触
外に出て歩くとDMNが活性化。スティーブ・ジョブズもよく“ウォーキングミーティング”をしていたとか。
● ② アートに触れる
美術館、音楽、詩などの「意味が曖昧なもの」は、連想力を刺激してくれます。
● ③ メタ認知を意識する
自分の思考を一歩引いて見つめる「メタ認知力」も、洞察を生む鍵。
● ④ 雑談を侮らない
意図しない会話の中にアイデアのタネがある。オフィスでの“偶発性”を意識的に作り出そう。
● ⑤ ストレスをコントロール
緊張状態ではDMNが働きにくくなる。「何もしない時間」も創造には必要。
「ひらめき力」は生まれつきの才能ではなく、年齢に関係なく後天的に育てることができる力です。脳の「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」は、ぼーっとしているときやリラックスしているときに活性化し、無意識のうちに情報をつなぎ合わせて新たな発想を生み出します。このDMNを活性化するためには、意識的に余白のある時間を持つことが有効です。たとえば、散歩や入浴、自然とのふれあい、アート鑑賞や雑談などが効果的です。また、既存の考えにとらわれず、柔軟な姿勢で物事を見ることも重要です。年齢に関係なく、日々の習慣や意識の持ち方次第で、誰でも“ひらめきやすい脳”を育てることができます。
◆第6章:創造性×キャリア形成──あなたの“次の10年”をどう設計する?
人生100年時代では、40代・50代・60代でも新しい挑戦が可能です。そのためには、「経験をどう活かして創造性に変えるか?」という視点が大切になります。
● 学ぶべき問い
-
あなたは、自分の“直感力”や“洞察力”を信じられていますか?
-
過去の経験を、次の創造にどう活かせそうですか?
-
年齢の違う仲間と、どうコラボレーションしていますか?
このような問いを自分自身に投げかけてみることが、創造的なキャリア設計の第一歩になるはずです。
◆まとめ:創造性とは「人生の深み」そのもの
最後に、茂木健一郎さんの言葉をもう一度振り返ってみましょう。
「人は、死ぬ直前まで創造的でいられる」
この言葉は、私たちが持つ“創造性”のイメージを覆します。創造性とは、若い人だけの特権でもなければ、技術や知識のことだけでもない。それは、人生そのものからにじみ出る「意味づけの力」なのです。
年齢を重ねるということは、人生の経験が積み重なっていくということ。そのすべてが、次のひらめきの“素材”になります。
創造性は消費されるものではなく、熟成されるもの。
今この瞬間も、あなたの中で新たな創造の種が育っているかもしれません。