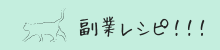◆ 「定年60歳」はどうして決まったの?そのルーツをたどってみたら…
今でこそ当たり前のように使われている「定年60歳」という言葉。
でも、そもそもなぜ60歳なのでしょうか?
実はそのルーツをさかのぼると、日本で最初に定年制度が登場したのは明治時代まで戻ります。
● はじまりは1887年。軍の工場からスタート
最古の記録は、1887年(明治20年)。
東京の「東京砲兵工廠(こうへいこうしょう)」という軍の工場で、55歳定年制が導入されたのが最初と言われています。
さらに、1902年には日本郵船が社員の規則で「55歳で休職・その後解雇」という制度を設けました。
当時の日本人の平均寿命は40代後半から50代前半だったので、定年55歳といっても、実際には定年を迎える前に亡くなる人が多かった時代です。
つまり、
「長く働いてくれてありがとう。余命の数年間はゆっくり休んでね」
という前提で作られた制度だったんです。
● 昭和初期には「50歳定年」が多数派
1933年(昭和8年)の調査では、すでに多くの工場で定年制度が採用されており、その定年年齢の主流は50歳か55歳でした。
-
50歳定年:全体の約57%
-
55歳定年:約34%
今の感覚だと「早すぎる!」と思いますが、当時はそれが「普通」だったのです。
● 定年60歳が義務化されたのは、実は最近
戦後、高度経済成長とともに寿命が延び、働ける高齢者も増えていきました。
その流れを受けて政府も動き、1986年の法改正で「60歳定年」が努力義務に。
さらに、1998年には60歳定年が法律で義務化されました。
つまり、私たちが当たり前だと思っていた「定年60歳」は、実はごく最近つくられたルールなのです。
● でも、今の私たちは「100年生きる時代」
2024年現在、日本人の平均寿命は…
-
男性:81歳
-
女性:87歳
定年後に20年、30年、下手したら40年もあるのに、制度は昔のまま。
いまだに「60歳=一線を退く」という前提が社会に根強く残っているのです。
● だからこそ、必要なのは「リスキリング」
これからは、定年後の時間こそ“もう一つのキャリア”。
学び直して、自分の価値を社会に届け続けることが、
定年後の「長い、でも充実した時間」を創るカギになります。
そのための準備が、リスキリング(Reskilling)=スキルの学び直し。
「定年制度」が生まれた背景を知ると、
これからの働き方を“自分でアップデート”する必要性が、ぐっとリアルに感じられるのではないでしょうか。
でも今や人生は100年時代。
60歳でリタイアしても、その後に40年近い時間が残されているのです。
その間、年金と貯金でのんびり過ごす…?
それとも、誰かに必要とされながら、自分のやりがいを持って働き続ける…?
「未来は選べる」と言いますが、選べるのは“準備していた人”だけ。
その準備のカギこそが、「リスキリング(Reskilling)=スキルの学び直し」です。
◆ アメリカの若者は「雇われるのはダサい」と言う
驚くかもしれませんが、アメリカではZ世代(1997年以降生まれ)のおよそ半数がフリーランスとして働いています。
つまり、「会社に雇われて働く」という形ではなく、
「自分のスキルで、自由に働く」
「いろんな仕事を掛け持ちして、自分の時間も大切にする」
といったスタイルを選んでいるのです。
実際、「Being employed is uncool(雇われるのはカッコ悪い)」というフレーズが、若者のあいだで広がっているという報道もあります。
◆ ハーバード卒の7割が起業? 変わるエリートの選択肢
かつてエリートといえば、卒業後は外資系コンサルや大手金融機関へ…というのが定番でした。
しかし、今やハーバード・ビジネス・スクール(HBS)卒業生のうち、7割がスタートアップを起業または参加しているというデータがあります。
スタンフォード大学では、2020年のMBA卒業生の約18%が卒業後すぐ起業しており、将来的には約半数が15年以内に起業に関わるというデータも。
たとえば、
-
Airbnb:スタンフォード大学の卒業生たちがルームシェアから始めたビジネス
-
Dropbox:HBS出身の創業者が「自分に必要だったから」作ったクラウドストレージ
など、世界を変えるような会社が、こうした流れから生まれています。
◆ 一方、日本では… まだ「正社員が安定」の神話が残っている
日本はどうかというと、2023年現在、**フリーランスの割合は全体の約6.9%**にとどまります。
これはアメリカの約半分以下。しかも「副業的なフリーランス」が多く、本業として成り立たせている人はごく一部です。
東大卒の進路にも変化の兆しはありますが、まだまだ「安定した企業に勤める」「転職はネガティブ」という意識が根強いのが現実です。
◆ なぜ日本ではリスキリングが進まないのか?
4つの「構造的な壁」
日本で「学び直し」が進まない理由には、次の4つの大きな壁があります。
① 年功序列と終身雇用の文化
いまだに多くの企業では、「スキルより年次が評価される」という体質が残っています。
例:ある大手メーカーで、20代の若手がAIを活用した生産ラインの効率化を提案したところ、「まだ早い」「余計なことをするな」と却下。
結局、アイデアは5年後に別の部門から採用され、若手は退職していました。
スキルや意欲が報われない環境では、学び直しのモチベーションは育ちません。
② 転職・スキルチェンジへの風当たりの強さ
「転職=根性がない」「すぐ辞める人」というイメージ、まだありませんか?
例:30代で金融機関を退職し、プログラミングスクールで学んだ男性がIT企業に応募したところ、「実務経験がない」「前職と関係がない」と10社連続で不採用に。
“やってみたい”よりも“即戦力”が重視される日本では、スキルチェンジが非常に難しいのです。
③ OJT頼みで、体系的な学習の場が少ない
「仕事は現場で覚えろ」「先輩の背中を見て学べ」文化がまだ根強い日本。
たとえば、クラウド技術やデータ分析の研修を希望した社員が「今の業務に関係ないから」と却下され、自費で夜間オンライン講座を受講していた事例も。
DXやAIのような最新スキルは、OJTではなかなか身につきません。
④ フリーランスになるとリスクが高すぎる
フリーランスになると…
-
雇用保険・傷病手当金・退職金 ⇒ ナシ
-
住宅ローン ⇒ 審査が厳しくなる
-
保険や年金 ⇒ すべて自分で手続き
例:子ども2人の父親が40代で独立し、収入が安定せず1年で再就職したケースも。
「好きな仕事をしたいけど、生活が心配で踏み出せない」という声は非常に多いのです。
◆ このまま何も変えないと、私たちの未来はどうなる?
今のままだと、多くの人がこうなります。
-
60歳で定年 → 再雇用で給料は1/3
-
やりがいも責任も減り、ただ座って時間を過ごすだけの仕事
-
自分の役割や存在価値を感じられないまま、80代へ…
想像してみてください。
「今日も1日何事もなかったな…」と、40年間思いながら生きる未来。
それ、本当に望んでいますか?
◆ ワクワクする未来を選ぶために
いま、学び直しを始めよう
一方で、人生100年時代は「チャンスが長く続く時代」でもあります。
-
50歳からでもスキルを磨き直してキャリアチェンジ
-
60代から新たな挑戦で社会に必要とされ続ける
-
70代で人生最大のヒット商品を生み出す――
そんな人生を歩んでいる人も実際にいます。
ポイントは、
-
お金や名誉のためではなく
-
「自分がワクワクすること」
-
「本当に成し遂げたいこと」
を軸に、自分の学びを再構築すること。
◆ 社会全体で変えていこう!リスキリング推進のカギ
日本社会がこのまま停滞せず、変革できるかどうかは、一人ひとりの学び直しがしやすい環境づくりにかかっています。
◉ キャリアの自律支援を広げよう
-
オンライン学習への補助制度
-
社内副業・越境学習の仕組み
-
社員のキャリア相談窓口の強化
◉ 転職や副業のしやすさを整えよう
-
経歴とスキルの「見える化」
-
フリーランスに優しい税制と保険制度
-
スキルマッチングの高度化
◉ 働き方の価値観をアップデートしよう
-
学校教育で「起業」や「プロジェクト型学習」の導入
-
チャレンジを称賛する文化の醸成
-
成功者・失敗者問わず、ロールモデルをもっと可視化
◆ 最後に——あなたが「自分の人生のリーダー」になるために
私自身、ビジネススクールでの学びを通じて、こう考えるようになりました。
「会社に評価されるかどうか」ではなく、
「社会や誰かに必要とされる自分でいたい」と。
だからこそ、私はリスキリングを“人生の軸”にすることを選びました。
あなたも、今日から少しずつ、自分の「好き」「得意」「学びたい」に目を向けてみてください。
「ただ席に座っている人生」から、
「ワクワクしながら誰かの役に立つ人生」へ。
一緒にその一歩を、踏み出しませんか?