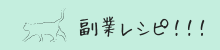■ はじめに:あなたは、管理職になりたいですか?
「管理職になりたくないんです。」
これは最近、私が仕事の中で耳にすることが増えた言葉です。
若手だけでなく、中堅層からも同様の声が聞こえてきます。
リクルートマネジメントソリューションズの調査(2022年)では、20代~30代の若手・中堅社員のうち「管理職になりたい」と回答した人はわずか2割程度という結果が出ています。「成長したくない」「責任を取りたくない」といった消極的な理由ばかりではありません。「自分のキャリアを自律的にコントロールしたい」「マネジメントより専門性を深めたい」といった、前向きな意思表示も含まれています。
とはいえ、企業としては深刻な問題です。プレイヤーは育っているのに、チームを率いる人材が不足していく。気づけば現場は、重たい責任を抱えた管理職と、マネジメントを避ける優秀なプレイヤーで構成された「サンドイッチ組織」になりつつあるのです。
この状況の背景には、単なる“意欲の低下”ではなく、管理職という役割に対する構造的な負担と曖昧さが潜んでいます。
■ 管理職が「しんどい役割」になってしまった理由
そもそも、なぜ管理職を敬遠する人が増えているのでしょうか?
その理由を大きく3つに整理してみましょう。
① 責任と負担が重すぎる
管理職は、チームメンバーの成果責任を負い、部下の育成、勤怠管理、評価、人間関係の調整など多くの業務を担います。業績達成だけでなく、メンタル不調への対応、ハラスメント防止、労働時間管理など、プレッシャーは年々高まっています。
特に日本企業では、プレイングマネージャーとして現場の業務も持ちながら、マネジメントも行う人が多く、常に「時間が足りない」「どっちつかずになる」悩みを抱えています。
② 報酬と権限が見合わない
昇進すれば給与が上がり、裁量も増える――かつての“出世のご褒美”としての管理職像は、すでに色褪せています。
成果主義やフラットな組織運営の広がりにより、給与差が小さくなったり、権限が思ったほど与えられなかったりするケースもあります。
結果として「責任は重くなったのに、メリットが感じられない」という認識が広がり、昇進に魅力を感じない人が増えているのです。
③ 管理職になる準備がされていない
多くの企業では、マネジメントのスキルや考え方を体系的に学ぶ機会がないまま、「実績があるから」「年次だから」といった理由で昇進が決まります。
評価や育成、部下のやる気をどう引き出すかといった実践的な知識が乏しいまま現場に放り込まれ、苦労するマネージャーは少なくありません。
■ 「マネージャー」と「リーダー」が混同されている日本企業
もうひとつ、根深い問題があります。それは、「マネージャー」と「リーダー」が混同されているということです。
日本企業では、「管理職=人を引っ張る存在」とされることが多く、マネジメントとリーダーシップの両方が求められます。ところが、これらは本来、異なる役割を持っています。
| 項目 | マネージャー | リーダー |
|---|---|---|
| 目的 | 組織の目標達成のための管理 | 人や組織を動かすビジョンの提示 |
| 手法 | 計画、管理、進捗確認、調整 | 動機づけ、共感、方向づけ、信頼 |
| 権限 | 役職によって付与される | 信頼や影響力に基づく |
| 特徴 | 機能的で制度的 | 感情的で文化的 |
欧米では、マネージャーとリーダーを分けて捉える文化があります。たとえば、GoogleやAppleでは、ピープルマネジメントを担うマネージャーと、技術的リーダーは別の人が担当することもあります。一方で日本企業では、「どちらもできる人=理想の管理職」という期待が強く、無理を強いているとも言えます。
■ 「リーダー的であること」も、実はハードルが高い
さらに、多くの人が「リーダー的であること」に対してもプレッシャーを感じています。リーダーシップという言葉に、カリスマ性や圧倒的な牽引力をイメージする人も多く、「自分には無理」と思ってしまうのです。
しかし、リーダーシップは必ずしもカリスマである必要はありません。
たとえば、次のような行動も立派なリーダーシップです。
-
会議で発言しにくそうなメンバーに「どう思う?」と声をかける
-
困っている人に「大丈夫?」とさりげなく手を差し伸べる
-
雰囲気が悪いときに「ちょっと空気変えようか」と笑顔で言う
これらはすべて、周囲の人に影響を与え、前に進むきっかけを作る行動です。
つまり、リーダーシップは「行動」であり、「肩書き」ではありません。
むしろ、「自然体のリーダーシップ」がこれからの組織には求められているのではないでしょうか。
■ 管理職不在時代に組織がすべきこと
「管理職になりたくない」人が増えていることを批判するのではなく、組織としては次のような対策が必要です。
● 管理職の仕事を“再定義”する
すべての業務をひとりで抱え込むのではなく、評価制度、人事部門、チーム内のサポートなどで役割分担と補完を行い、「リーダーシップ発揮」や「人間関係構築」に集中できる環境をつくることが重要です。
● マネジメント教育の早期化・平準化
プレイヤー時代から、チームを支える経験を積ませたり、ロールプレイやOJTを通して段階的にマネジメントスキルを習得させたりする仕組みが求められます。
● キャリアパスの多様化
マネジメントに進まなくても、専門性やプロフェッショナリズムで評価されるルートが整備されることで、「無理に昇進しなくても報われる」安心感が生まれます。
■ おわりに:再定義が必要な「管理職」のかたち
「管理職=なりたくない」
それは、個人の怠慢ではなく、役割が肥大化し、期待と報酬が釣り合わなくなった結果です。
いま企業が向き合うべきは、「どうすればマネージャーが楽になるか」ではなく、
「どうすればマネージャーの仕事が意味あるものに再設計されるか」です。
そしてその再設計には、「リーダーシップとは何か?」という問いが欠かせません。
次回は、「マネージャーとリーダーはどう違うのか?日米の比較から見える構造のズレ」をテーマに掘り下げていきます。