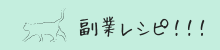■ はじめに:いま、上司を「外注」する時代?
最近、「管理職代行サービス」という言葉を耳にしたことはありませんか?
たとえば、こんなサービスがあります。
-
評価・フィードバック・目標設定といった人事マネジメントを、外部の専門家が請け負う
-
現場のメンターや人材育成担当を、外注のコンサルタントが担当する
-
社内に管理職がいない新規事業部門に、外部の“仮想マネージャー”を配置する
一見すると、画期的な解決策のように見えます。
たしかに、「なりたくない管理職」「育てられない管理職」「育成する時間がない企業」にとって、管理業務の外注はとても魅力的に映るでしょう。
しかし、ここで立ち止まって考えたいのです。
マネジメントは代行できても、リーダーシップは外注できるのか?
この問いが、いま組織にとって非常に重要になっています。
■ なぜ、管理職代行が注目されているのか?
まず、管理職代行やマネジメント外注が求められている背景を整理してみましょう。
① 社内にマネージャー候補が不足している
前回までの記事でも触れたように、「管理職になりたくない」人が増えています。
一方で、企業側としては「プレイヤーだけの組織」では限界があるため、“外からマネジメントを借りてくる”という動きが広がっているのです。
② 育成・評価に関する専門性が求められる
評価制度が多様化し、フィードバックの方法も高度になってきた今、
「現場のリーダーが人事的なマネジメントまで担うのは難しい」という声も増えています。
そこで、人材育成やコーチングの専門家に“外注”する流れが出てきました。
③ 組織の立ち上げフェーズではスピード優先
特にスタートアップや新規事業チームなどでは、「社内に人がいないから外から補う」という判断がなされます。
“0→1の立ち上げ”と“定着・育成”を切り分けて、まずは外部に任せるというケースも珍しくありません。
■ 代行できる“管理職の機能”とは何か?
ここで一度、「管理職の役割」を分解してみましょう。
| 管理職の業務 | 代行の可否 | 理由 |
|---|---|---|
| 目標設定・KPI管理 | 代行可能 | 組織戦略を踏まえた設計が可能。コンサル型で対応しやすい。 |
| 進捗管理・業務調整 | 代行可能 | 外部でも数値やデータに基づいて対応できる。 |
| 評価・フィードバック | 一部代行可能 | 制度に沿って運用できるが、関係性が浅いと限界あり。 |
| 育成・メンタリング | 限界あり | 外部でも対応できるが、日常の観察や信頼関係の蓄積が必要。 |
| チームの雰囲気づくり | 基本的に不可 | 「空気をつくる」「共に悩む」といった行為は、内側の人間にしかできない。 |
| 信頼の構築 | 外注不可 | 継続的な関わり・文脈の理解が前提となる。 |
つまり、「業務の管理・制度の運用」は外注できても、「人との関係性」は外注できないということです。
■ リーダーシップの「代行」はできない
管理職の機能のうち、最も“代行できないもの”――それがリーダーシップです。
なぜなら、リーダーシップとは「この人の言葉なら信じられる」「一緒に働きたい」と思わせる力だからです。
それは、肩書きやスキルではなく、日々の関わりと信頼の積み重ねによってしか生まれません。
外部の専門家がどれほど有能であっても、
「この人は自分たちと同じ目線で考えてくれている」
「この人になら相談してもいい」
――そう思ってもらえるまでには、時間と関係構築が必要です。
■ 「管理職の分業」と「リーダーシップの内製化」のバランスが鍵
これからの組織には、次のような“役割のバランス感覚”が必要になります。
✅ 外注・代行で解決できること
-
制度運用の専門性(評価制度・1on1の設計など)
-
業務プロセスや目標管理の形式的支援
-
初期フェーズでの立ち上げ支援(短期介入)
✅ 内部でしかできないこと
-
日々のちょっとした声かけ、観察、対話
-
チームの文化や空気づくり
-
信頼と共感をベースにしたリーダーシップの発揮
特に重要なのは、「マネジメント業務は支援・分担しながら、リーダーシップは社内に育てていく」方針を明確にすることです。
■ 管理職を「減らす」のではなく、「再設計」する時代へ
代行サービスの広がりは、管理職の仕事が「抱え込みすぎていた」ことの証明でもあります。
プレイヤーとしての業務+マネジメント+評価+育成+メンタルケア……
1人で全部やるのが当たり前だった時代から、役割を再設計して、チームで補い合う時代へと、シフトする必要があるのです。
-
評価や制度面は人事や外部に任せる
-
チームビルディングは複数のメンバーで担う
-
自然体のリーダーシップを発揮できる“非公式リーダー”も評価する
そんな柔らかい構造が、これからの組織の当たり前になっていくでしょう。
■ おわりに:人を動かす力は、いつの時代も「内側」にある
マネジメントは分業できます。外注もできます。
でも、人を本当に動かす力――それは、「この人と一緒に働きたい」と思わせる関係性の中にしかありません。
リーダーシップは代行できない。
だからこそ、管理職というポジションの重さを、もっと等身大に、自然体に捉え直すことが必要なのだと思います。
🎯 4回連載を通して伝えたかったこと
-
管理職になりたくない人が増えているのは、怠慢ではなく「構造の問題」
-
マネージャーとリーダーは異なる役割であり、両立を当然とするのは酷
-
リーダーシップは誰でも発揮できる「行動」であり、自然体であっていい
-
管理職の仕事は分解・再設計すべき。外注すべきものと、内側で育てるべきものがある
📚 連載を読んでくださったみなさまへ
このシリーズが、あなたの職場でのあり方や、チーム作りのヒントになれば幸いです。
感想やご意見があれば、ぜひSNSやコメント欄でお聞かせください!