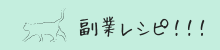まさかの「18時30分職場見学」に20人で残業?
先日、職場でちょっとした波紋が広がりました。
ある日の午後、チャットに届いた一言。
「〇月〇日、18時30分からお客様が職場を見学されます。
各チーム5人以上の出社をお願いします。」
え?定時は18時までだよね?
しかも、職場は普段ほぼリモートワーク。
その時間に、なぜリアル出社で“にぎわい演出”が必要なのか?
みんなが静かに反応を見守るチャットの空気に、私は強烈な違和感を覚えました。
お客様対応という名の“残業要請”、リモート空間の空気は重い
今回見学に来られるのは、マネージャークラスのお客様。
いわゆる「見学的なご訪問」であり、直接の意思決定者でもありません。
にもかかわらず、なぜほぼチーム全員で残業?
しかも、こうした動員指令が下されたのは、現場に近い管理職ではなく、その上の管理職の人から。
“誰もが逆らえない立場”からの発言に、リモートのチャット空間は一気にモヤつきました。
「無駄な動員」がもたらす心理的コストとモチベーション低下
「何のために?」「自分たちが“背景”になるだけ?」
同僚たちのチャット返信が止まり、表情の見えない会話が漂い続けます。
-
残業の強制に近い圧力
-
残業する意味への納得感のなさ
-
モチベーションの微妙な低下
これはまさに、心理的安全性が崩れかける瞬間でした。
職場における「声を上げづらい空気」は、小さなきっかけで簡単に生まれます。
提案したけれど…結果は“人数が減っただけ”
私は意を決して、上司に控えめに提案を伝えてみました。
-
本当に合計20人も必要なのか?
-
来客の目的を踏まえれば、数名の対応で十分では?
-
普段の様子を伝える資料やスライドで補完できないか?
上司は一部には耳を傾けてくれたものの、「人数を少し減らす」程度で調整が終わりました。
スマートな対応にはなりきれなかった。
私の伝え方や提案の甘さもあったと、正直反省しています。
働き方の違和感を見過ごす組織文化と、私たちのリーダーシップ
この一件を通じて、私はあらためてこう感じました。
-
無駄な動員の構造は、組織文化に内在する“儀礼主義”や“形式重視”に根ざしている
-
上からの指示が“空気を支配”する構図では、現場の声は届きにくい
-
それでも、違和感を言語化して伝えるのは現場にいる私たち一人ひとりのリーダーシップ
まとめ:定時後の“静かな圧力”を見逃さないで
「たかが30分の残業」と思うかもしれません。
でも、その小さな動員の積み重ねが、働き方への不信感を生むことがあります。
定時後の無言の残業要請、心理的安全性の揺らぎ、職場の沈黙。
それを「まあ、しょうがないよね」で済ませるのか、
「ちょっとおかしいかも」と立ち止まるのか。
この記事が、そんな“職場あるある”の奥にある課題を考えるきっかけになれば幸いです。
📚 おすすめ書籍:働き方の違和感にモヤっとしたら読みたい3冊
1. 🧠 心理的安全性をどう職場に根付かせるか
『心理的安全性のつくりかた』石井遼介(英治出版)
Googleが注目した「心理的安全性」を、日本の組織文化にフィットさせるための実践書です。
誰もが“ちょっとおかしいな”と思っていても言えない。
今回のような「チャット上の沈黙」や「暗黙の圧力」こそ、まさに心理的安全性が欠けた状態。
この本は、リーダーやマネージャーが無意識に作っている“発言しづらい空気”にどう向き合うかを、豊富な実例とともに教えてくれます。
2. 🌱 組織の前提を疑ってみる
『ティール組織』フレデリック・ラルー(英治出版)
「なぜ20人も残業しないといけないのか?」という疑問は、実は組織の在り方そのものに関わる問いです。
本書では、従来のヒエラルキーや管理型マネジメントを超えて、目的駆動・自律分散型の「ティール組織」の実例を紹介しています。
“動員すればするほど誠意がある”という価値観から脱却し、納得感のある働き方や職場運営にどう転換していくか。そのヒントが詰まっています。
3. 🤝 上司・部下の間にある“分かり合えなさ”の正体
『なぜ部下とうまくいかないのか』高橋俊介(日本経済新聞出版)
「なぜあの上司は、ああいう動員指示を出すのか?」
「なぜ上司に意見しても響かないのか?」
そんな疑問を、キャリア論や組織行動論の視点から解きほぐしてくれるのが本書です。
ミドルマネジメントやそれ以上の管理層が陥りがちな「形式主義」や「責任回避構造」にどう向き合うか。
現場と経営の“翻訳者”としての役割にヒントをくれる一冊です。
「たかが30分の残業」「たかがお客様対応」と流してしまいそうなことにも、
実は組織文化やマネジメントの深層が表れていることがあります。
今回のような体験をきっかけに、「なぜ?」を掘り下げてくれる本を手に取ってみませんか?