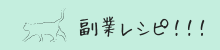はじめに:なぜ今、定年後の後悔に注目するのか
日本は世界有数の長寿国となり、いまや「定年後30年」の人生をどう生きるかが、現役世代の重要なテーマになっています。近年の調査では、多くの定年退職者が「やればよかった」「やっておいて本当によかった」と感じた経験を語っており、そこには“今を生きる私たち”への貴重な示唆が詰まっています。
本稿では、日本の典型的なサラリーマンが定年後に後悔すること、満足することを掘り下げるとともに、それを現役中に実行できない構造的・心理的な要因を明らかにしていきます。そして、後悔を減らすための実践的なヒントを提示します。
1. 「やればよかった」「やってよかった」と感じる4つの領域
定年後のサラリーマンが語る後悔と満足には、以下の4つの領域が浮かび上がります。
-
お金(資産形成・使い方・投資)
-
仕事(スキル・働き方・自己実現)
-
家族・人間関係(配偶者・子ども・友人)
-
健康(運動・習慣・歯・禁煙)
それぞれの領域で「やればよかった」「やってよかった」と語られる具体例を紹介し、それを阻んだ理由を探ります。
2. お金編:「もっと早く投資すればよかった」「家族のために使えばよかった」
◆ 定年後の声:
-
「投資や資産運用を早く始めていれば…」
-
「家の購入は正解だった」
-
「もっと家族旅行や自己投資に使えばよかった」
◆ 現役中に実行できない理由:
① 長時間労働で“考える余裕”がない
日本のサラリーマンは世界でもトップクラスの勤務時間を誇ります。早朝から深夜まで働く中で、資産運用や老後資金計画に頭を回す時間が取れないのが実情です。
また、生活費や教育費、住宅ローンなど目先の支出が重くのしかかり、「貯める」「増やす」余裕を失いがちです。
② 金融教育の欠如と“投資=怖い”の思い込み
日本では学校教育や職場で金融リテラシーを学ぶ機会が乏しく、NISAやiDeCoの活用も進んでいません。「失敗したら怖い」「損したら取り返せない」といった感情が、投資に踏み出すことをためらわせています。
③ “男は稼ぐ、女は守る”という固定観念
戦後の高度成長期を経て築かれた価値観では、「家庭のために稼ぐ」が美徳とされ、自己投資や趣味、旅行などにお金を使うことは“贅沢”だとされてきました。その結果、自分や家族の幸せのためにお金を使う習慣が身につかないまま定年を迎えるケースも多いのです。
3. 仕事編:「もっと好きな仕事をすればよかった」「スキルを磨いておけばよかった」
◆ 定年後の声:
-
「やりたい仕事を見つけておけばよかった」
-
「外国語を勉強しておけば再就職に有利だった」
-
「資格を取っておけば選択肢が広がった」
◆ 現役中に実行できない理由:
① 組織内キャリアに縛られた発想
日本企業では今なお年功序列が根強く、配置転換や異動は“会社次第”で決まります。本人が「やりたい」と思っても異動や転職にリスクが伴い、現状維持を選ぶ人が多いのです。
② キャリアの“主導権”を握れていない
欧米に比べて「自分のキャリアを自分で描く」という発想が弱く、「会社が用意するレールに乗ってきたら定年になった」という声も少なくありません。主体性が薄いまま職業人生を終えると、振り返ったときに強い後悔を残します。
③ 学び直しに時間とエネルギーが割けない
リスキリングや語学学習、資格取得などに関心はあっても、仕事と家庭の板挟みで時間を確保するのが難しいのが現実です。夜間学校やオンライン講座などの情報にも触れる機会が少なく、行動に移す人は少数派です。
4. 私生活編:「親孝行すればよかった」「配偶者や子どもともっと関われたのに」
◆ 定年後の声:
-
「もっと親孝行すればよかった」
-
「家族旅行の時間を大事にすればよかった」
-
「友人関係を大切にしておけばよかった」
◆ 現役中に実行できない理由:
① 「仕事=家族のため」と信じて疑わなかった
高度経済成長期に形成された「仕事に打ち込むことが最大の家族サービス」という価値観は、いまなお多くのサラリーマンに浸透しています。その結果、長時間労働で家にいない、家族とすれ違う生活を「仕方ない」と諦めてしまいがちです。
② プライベートを後回しにする文化
会社最優先の風土の中では、友人との付き合いや趣味を「わがまま」「遊びすぎ」として否定されやすく、結果的に孤独な定年後を迎える人も少なくありません。
③ 男性の“感情表現の不得手さ”
日本の中高年男性は、感情を表に出すことや「ありがとう」「ごめんね」といった言葉を素直に伝えることが苦手な人が多い傾向にあります。そのため、家族との距離が広がってしまうのです。
5. 健康編:「タバコをやめればよかった」「運動を習慣にすればよかった」
◆ 定年後の声:
-
「歯を大事にすればよかった」
-
「もっと歩けばよかった」
-
「タバコをやめておけばよかった」
◆ 現役中に実行できない理由:
① 健康は“失ってから気づく”もの
若いころは体力もあり、睡眠不足や偏った食生活も大きな影響を感じにくいものです。そのため「健康は後回し」にされがちで、気づいたときには取り返しのつかない状態になっていることもあります。
② 健診結果の軽視と歯科ケアの軽視
多くの企業では定期健診が義務付けられていますが、その結果を真剣に受け止め、生活習慣を変える人は多くありません。また、歯の健康は見落とされがちで、「噛めない」「喋れない」といった支障を定年後に感じて後悔する人が多いです。
③ “男は強くあるべき”という無意識の圧力
健康に不安があっても「我慢」「気合」で乗り切ろうとする傾向が日本男性には根強くあります。病院に行くことを“弱さ”と捉え、受診や改善を先延ばしにしてしまうのです。
6. 構造的な背景:「忙しさ」と「文化」が行動変容を阻む
ここまで見てきたように、多くの「やればよかった」は、現役時代の“忙しさ”と“社会文化”に根差しています。言い換えれば、それは本人の意志の弱さというよりも、日本社会が作り上げたサラリーマンの構造的限界と言えるでしょう。
-
忙しさが思考と行動の余裕を奪う
-
会社中心主義がプライベートを軽視させる
-
男性像に縛られ、感情や健康への配慮が不足する
-
お金やキャリアについて語る機会が少ない
7. では、どうすればいいか? 後悔しない人生をつくるために
最後に、後悔を減らすために今からできる行動をいくつか提案します。
-
毎月「振り返りと未来設計」の時間をつくる
自分の価値観・働き方・お金・人間関係・健康を定期的に棚卸しし、「このままでいいか?」を問い直す習慣を持つ。 -
小さく始める
週1回のウォーキング、月1万円の積立投資、月1回の親への電話——小さな一歩が、大きな後悔を防ぎます。 -
対話を増やす
職場や家庭、友人と「これからどう生きたいか」を語る機会をつくることで、選択肢の幅が広がります。 -
“誰かのため”から“自分のため”へ発想を変える
人生後半は「会社のため」「家族のため」から脱却し、「自分がどう生きたいか」に素直になることが大切です。
おわりに
「やればよかった」「やってよかった」の声は、後悔と成功の集積であり、私たちが未来をより良くするためのヒントでもあります。
今のサラリーマンが、次世代のモデルとなるような後悔の少ない人生を築けることを願ってやみません。
いつ始めても、遅すぎることはありません。今日から、一歩を。