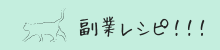30代・40代で学ばないと、組織の未来戦略が描けなくなる理由
今日は、ちょっと心に引っかかる出来事がありました。
来年度の組織目標を決めるためのミーティングがあり、私を含めたマネージャー陣5人と、その上のリーダーが集まりました。テーマはシンプル、「来年、私たちのチームはどうありたいか?」。その場で出し合ったアイデアをもとに、方向性を定めていく予定でした。
でも――全然、意見が出てこないんです。
無言の会議が示す、マネージャーのスキル不足とその影響
その場は、ファシリテーターもいて、あくまで「自由に出し合おう」というスタイルでした。確かに、議論を促すための資料や枠組みはなかったし、「こういう視点で考えてみよう」といった誘導もなかった。
でも、それにしても。
参加者のほとんどは、無言のままパソコンに目を落としたまま。
一人ひとり、現場では経験も豊富で、部下の支援やトラブル対応には力を発揮している優秀な人たちです。なのに、組織の未来について語るとき、誰も口を開かない。
私はとてもショックを受けました。
そして、こう思ったんです。
社会人の自己研鑽不足が招く、組織マネジメントの停滞「勉強してこなかった」ことの代償
なぜ意見が出ないのか。
理由はいくつかあると思います。
• 日々の業務に追われて疲れ切っている
• 「自分ごと」として考える意識が薄い
• そして何より、未来の組織について考える経験や知識がそもそも足りていない
特に最後の点は、深刻だと感じました。
おそらく彼ら彼女らは、30代・40代のいちばん忙しい時期を、「目の前の業務をこなす」ことに全力で取り組んできたはずです。それで評価もされ、役職も得た。でもその間に、組織マネジメント・リーダーシップ・ビジネスの原理といった「中長期を考える視点」は、学ぶ機会がほとんどなかったのではないかと思います。
5年後を語れないマネージャーが増加中:リスキリングの重要性
今、企業では「次の世代のリーダーが育っていない」という悩みがあちこちで聞かれます。
でも、もしかしたらそれは「育っていない」のではなく、「育てられなかった」「学ぶ余裕を与えられなかった」のかもしれません。
正直なところ、私も責任を感じています。
私は彼らの直接の上司ではありませんが、同じマネジメント層として、「もっと早く、学ぶ時間を確保すべきだった」と。
30代・40代は“技術者”から“経営者視点”へと転換するタイミング
忙しい30代・40代だからこそ、本当は学ぶべきなんです。
• チームや組織の方向性をどう描くか
• ビジョンをどう共有するか
• メンバーのやる気をどう引き出すか
• 変化にどう対応し、どう進化させていくか
これらは、現場での経験だけでは身につきません。
書籍やセミナー、社外との交流、学び直しのプログラム――
自ら「知ろう」としない限り、得られない視点です。
「忙しいから学べない」ではなく、「学ばないから未来が見えない」
私は今日の出来事を通じて、強く感じました。
“学ばなかった”ツケは、必ず組織に返ってくる。
それは、誰かの責任ではなく、私たち自身の選択の積み重ねです。
だからこそ、今30代・40代の方には声を大にして伝えたい。
未来を描くために、今こそ社会人の学び直しが必要な理由
仕事が忙しくても、少しずつでいい。
月に1冊、本を読むだけでもいい。
週に1時間、誰かと対話するだけでもいい。
あなたが学び直すことで、あなたのチームは前に進める。
そして何より、自分自身が変わっていける。
40代50代で“ただ席に座っているだけ”の自分を望むのか、
60代70代になっても社会に必要とされる自分でありたいのか――。
選ぶのは、今のあなた自身です。